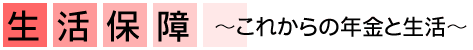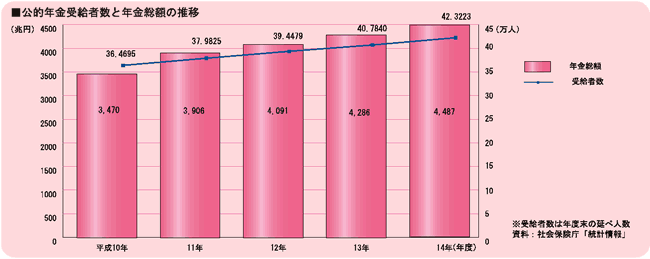年金制度の転換期を迎えた今、これまでのように定年まで勤めあげれば老後は年金生活で安泰といった時代は終わろうとしています。こうした時代の変化の中で、年金と現役時代の貯蓄だけに頼る生活は、リスクを伴う場合もあることでしょう。長期化する定年後の生活をより安定したものにする最大の自己保障は、働く意志と能力と体力がある内はできる限り働き続け、収入を自身で得ることです。
例えば、老齢基礎年金の受給開始年齢になっても年金を受け取らず、受給の開始を任意に遅らせる「繰り下げ受給」を行った場合、繰り下げ1か月あたり約0.7%ずつ支給金額が増額(5年間繰り下げた場合42%増額)されるなど、年金制度自体もより長い間自立した生活を送る高齢者に有利な仕組みとなっています。この制度を利用するかどうかによって、その後の年金受給額に大きな差が出てきますが、そのためにはまず、定年後の生活をできるだけ年金に頼らずに暮らせるだけの経済力が必要となります。こうしたことからも今後、定年後の再就職は老後のライフプランに欠かせないステップとなるでしょう。 |